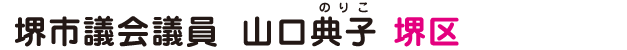午後1時から。本館12階委員会室にて。
議会力向上委員会で、
議会基本条例を策定している中で、
専門家からの研修会を開催することとなりました。
今日の講師は、
東京財団研究員、
早稲田大学マニフェスト研究所客員研究員、
第30次地方制度調査会委員の中尾 修さんです。
テーマは
「全国に広がる地方議会改革」 〜議会基本条例から考える〜。

中尾 修さん
Resume
1、地方議会の仕組み(二元代表制から)
2、住民との直接対話「議会報告会」の意義
(1)直接対話から得られるもの
(2)政策につなげることができるか
3、議会基本条例
(1)徹底した情報公開と共有・住民参加
(2)幻の1条
(3)反問権と自由討論
(4)長期行政計画への関与
(5)必須3要件(東京財団モデル)
4、市民参加の重要性
5、地方分権の今後(第30次地方制度調査会)
=要旨=
・名古屋市、阿久根市の例から、
議会は恒常的に市民との直接対話の回路を持っておくことが重要。
・議会改革は市長提案の議案に対し是々非々で臨むことが基本。
・議会基本条例は何のためにつくるのか、ということの整理が必要。
徹底した情報公開と市民参加によって、
議会評価、行政評価を受けていくことが当然。
・地方自治法だけでは時代を乗り切れない。
・ここまで行政権が肥大化した国も少ない。
・議会は行政執行の追認をしていた。
・行政という権威と市民の無関心の狭間に
議会が果たすべき役割がある。
・福島県会津若松市議会は一昨年制定した議会基本条例に
「議決責任」を盛り込んでいる。
・議案がじわりじわりと増えてきているはず。
・今まで国の通知は首長だけであったが、
総務省からは議長あてに来ているはず、
ということは従来よりも議会の権能が大きくなってきている。
・地方自治法を独自に解釈して乗り越えていってほしい。
29次の地方制度調査会ではそのことを定めている。
・議会基本条例が市民にとって使いやすい、
有効なものにする必要がある。
・自治体の予算縮減で市民に負担を強いる決断を求められ、
議会も説明責任を負うことになる。
・地域の要望を行政側に口利きするだけの
旧態依然とした議会では、その重さに耐えられない。
(神奈川新聞2011年5月30日記事より)
・堺市の議会基本条例にも
「議会報告会」は少なくとも年1回以上と明記すべき。
・請願・陳情者の意見陳述
・議員間の自由討議の3項目が必須条件。
・これを入れれば、政令指定都市で初めて
市民に有効な議会基本条例となるだろう。
・市民とともにつくる議会基本条例であることが重要。
・議員の個人の議員活動と同時に
・日本中の有権者が議会広報という政治的背景があるものを
100%信用していない。
・全国1700自治体の中で議会基本条例を策定した自治体は
今年の6月の時点で300を超え、第2ステージに入った。
・条例の策定の段階から市民の関心を持ってもらう手法を
実施することが大事。
・教育委員会や選挙管理委員会、農業委員会などの人事案件も、
首長の根回しなどで承認されるが、それも議決責任。
首長が提案だけ、決めるのは議会。
・ビデオでNHKの視点論点から
夕張市と栗山町の議会力の格差を検証。
・質疑応答
・35%の高齢化率を視野に入れて、
向こう10年の市の経営者としての経験が必要
・政党政治も含めて、代表制民主主義が
世界的に揺らいできていることの認識。
・幻の1条というのは、議員を選出した市民、有権者の責任。
出席議員
吉川敏文議長、米谷副議長、
議会力向上委員会委員、
西村、水の上、馬場、長谷川、裏山、松本、池田、森、城、野里。佐治、西林、吉川守、山口
自由参加
北野、筒井、榎本、小西、宮本、成山、高木、芝田、山根、米田、黒田、池側、三宅、木畑、小林、源中、田中ひろみ、田中丈悦、西田、乾、石本、石谷、中井、上村、深井、井関、
(敬称略)
議会事務局職員

今日の研修会はとても有意義でした。
頭の中で考えていてもなかなか議会全体として
改革していくというのは大変な作業です。
賛成か反対かという二者択一の議決だけではなく、
議論が必要だということです。
必ず来る、財政危機への危機感を持ちながら
人口動態の変化を見つつ
しっかりとした経営が必要というアドバイスは的確でした。
今日のお話をしっかり参考にしながら、
堺市の議会基本条例の策定作業に関わっていきます。