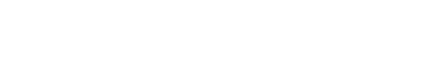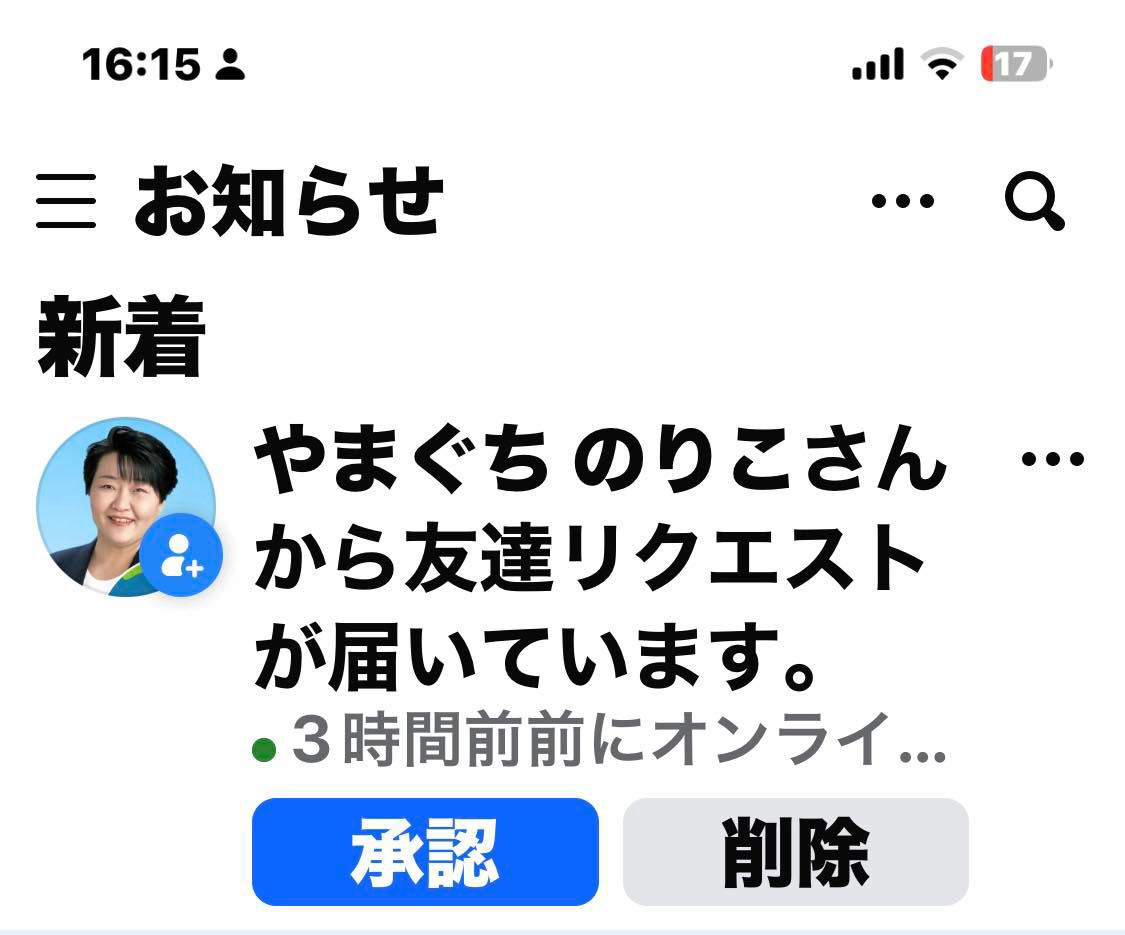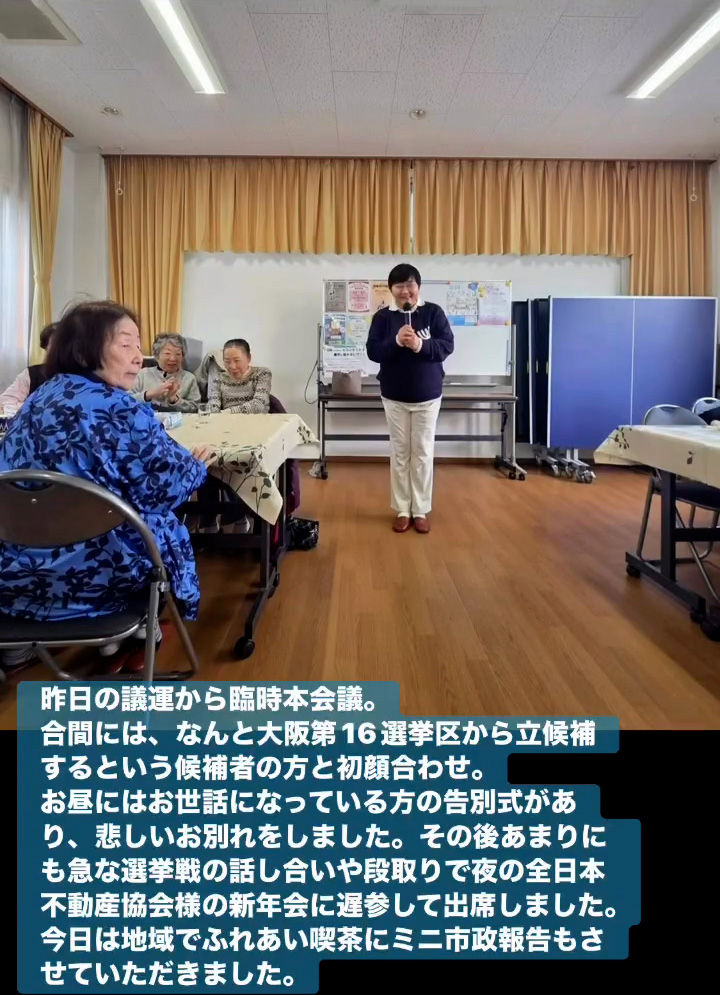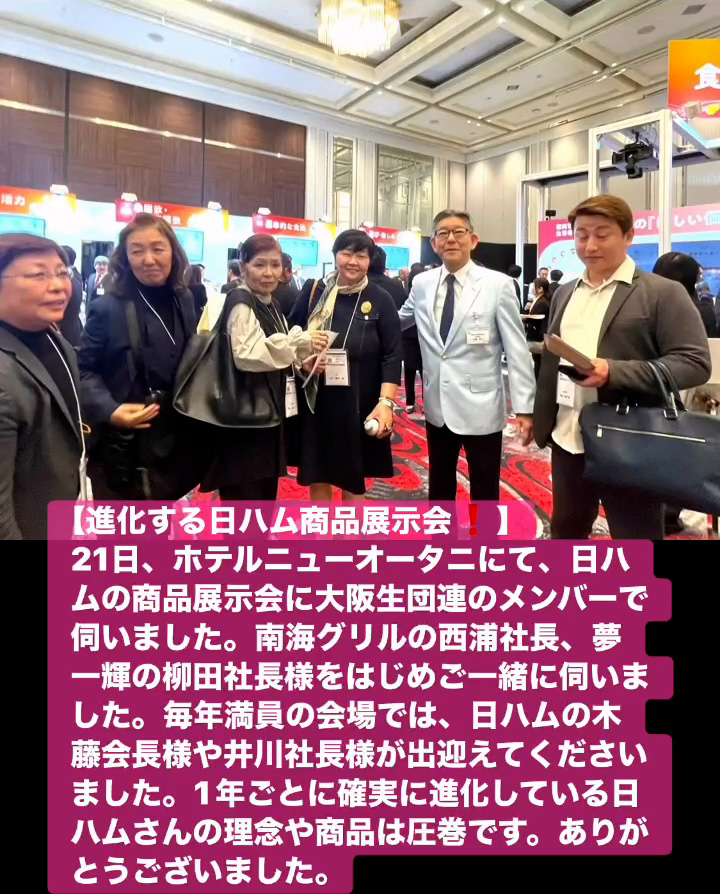昨日の午前中に、都市計画審議会が行われました。
憲法第29条に基づいた都市計画法によって、市民主権によるまちづくりを行う重要な会議です。
今日は、何度か発言をさせていただきました。(そもそも報酬のある審議会で、なんら発言もしない委員については、他の審議会においても対応を考えないといけないと思います。)
ともすれば、都市計画審議会は、市街化区域にするかしないか、生産緑地の決定をどうするか、都市計画道路等にするかしないかなどの判断をするための判定会議になりがちですが、もっと堺市全体を俯瞰しながら、産業振興や市民の物理的、精神的な安全安心も含めて、個別の案件を審議する必要があると考えます。
例えば今日の案件の建物の容積率の緩和について、事業者等の取り組みの評価項目についても、もっと市民の皆様の利便性や安全を考え、たとえば、誰もが使えるトイレの設置や防犯カメラや防犯べる、また防犯灯などの設置の取り組みを推進することを提案しました。
さらに災害の際の避難所設営や帰宅困難者の一時避難所設営をされる事業者にはもっと容積率をアップする必要があることも提案しました。
市民生活の安全には、日本で堺市しか取り組んでいないセーフシティ・プログラムのこともまったく出てこなかったのは残念ですね。
建築都市局だけでもかなりたくさんの職員さんが出席していましたが、議案についての取りまとめなどをどこか民間のコンサル業者にでも委託しているのか、ほとんど堺市のオリジナリティが見えないですね。
今日の会議で指摘しましたが、堺市のマスタープランの理念を見ても、時代遅れ感満載です。DXも生成AIの文字も見当たらず、新しい時代に対応した市民生活のイメージや未来の希望が感じられません。
また、大店法の廃止によって、中心市街地が衰退しているのは、堺市だけではなく全国的な現況であることを踏まえて、早急に対応する必要があります。
今日の案件は北野田と新金岡地域の話でしたが、それも中心市街地や中百舌鳥、臨海部など全区を含めた堺市全体で考えていく必要があると思います。
まちづくりについて、やっていることが局ごとにバラバラですから、それを整理するのも実は都市計画審議会の役割であるはずです。
いつのまにか役所に都合のよいやり方の会議になってしまっているようですね。
今日で辞任される嘉名光市会長も最後のご挨拶で、他市の都計審は若い委員枠を設けたり、事前会議を開いて自由闊達な意見交換が行われている。都計審は、まちづくりに制限を課すことができる、ということは大きな権限を有しているので、だからこそ住民の人権等に十分に配慮する必要がある、とおっしゃっておられました。
こんな素晴らしい専門家の嘉名教授がなぜお辞めになるのか?と尋ねると「就任期間が長いから」とのことでした。一定のルールはあるものの、もったいない人事だと思うのは私だけでしょうか。
どこの審議会も市長の諮問に応えていくわけですが、政策の立案や合意形成の一助として重要な役割を持っています。
審議が機械化、事務化、形骸化しないことが大切です。
そういう意味では、どの審議会も要旨だけではなく、しっかりとした議事録を公開することも大切ですね。